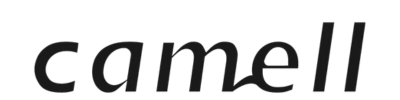ロベール・ドアノーと言えば有名な『パリ市庁舎前のキス』この写真がブームになったのは高校生の時で、先輩がドアノーに熱烈愛を語っていたのを
”ふーん”とみていた後輩の私。
東京都写真美術展は、コロナ前のCP+に行ってた頃から行ってみたかったとこで、
実に5年をかけてたどり着いた場所。
歴史的な写真に気持ちが解放されていく
ちょっとチェックしていただけの写真展。
有名な写真家の写真展だし、ちょっと見ておくかー。位のノリでチェックしてて、アートアプリから『もうすぐ終了ですよ』とリマインドが。
場所は恵比寿。宇都宮から電車乗り換えなしでいけるし、予定も空いてる。
このたび東京都写真美術館では「本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語」展を開催いたします。
本橋成一は東京に生まれ、50年以上にわたり、写真と映画によって、揺れ動く社会とそこに暮らす人々の姿を記録してきました。
一方ロベール・ドアノーは、パリや自身が生まれたパリ郊外を舞台として、常にユーモアをもって身近にある喜びをとらえてきました。
生まれた時代・地域が異なる二人の写真家ですが、奇しくも炭鉱、サーカス、市場など、同じテーマによる優れたルポルタージュを残しています。そして、それぞれに第二次世界大戦による混乱を経験した二人は、慎ましくも懸命に生きる人々の営みの中に、力強さと豊かさを見出し、失われゆく光景とともに写真に収めてきました。
多くの対立、紛争の絶えない現代において、人間に対する際限のない愛情と好奇心が生み出す視線、そしてユーモアや優しさをもって現実や社会と関わった二人の写真家によって編み出される物語を通して、生きることの豊かさについて考える機会となれば幸いです。
本橋成一|Motohashi Seiichi
1940年東京・東中野生まれ。1960年代から市井の人々の姿を写真と映画で記録してきた写真家・映画監督。1968年「炭鉱〈ヤマ〉」で第5回太陽賞受賞。以後、サーカス、上野駅、築地魚河岸などに通い、作品を発表。写真集『ナージャの村』で第17回土門拳賞、映画「アレクセイと泉」で第12回ロシア・サンクトペテルブルグ国際映画祭グランプリを受賞するなど国内外で高い評価を受けている。
ロベール・ドアノー|Robert Doisneau
1912年パリ郊外のジャンティイ生まれ。エコール・エスティエンヌで石版を学び、写真家アンドレ・ヴィニョーの助手となる。自動車会社ルノー社のカメラマンなどを経て、1939年フリーとして活動を開始。特にパリの庶民たちの日常をとらえた写真で高い評価を得て、ニエプス賞(1956年)、フランス国内写真大賞(1983年)など受賞多数。1994年逝去(享年82歳)。
恵比寿駅で電車を降りて改札をぬけ、目的地へ。
恵比寿ガーデンプレイスに来たのも、しばらくぶり過ぎて浮かれてる。
エレベーターで上の階にあがり展示室へ。
展示室や作品は撮影禁止なので、頂いた作品リストに感じたことをメモすることにした。
目を閉じ。すぅ…と息を吸い込んで、自分を囲む城壁を外すようなイメージ。
そうやって、感覚を無防備に解放すると、
言葉や色や階調の振動がわたしに響いて広がってゆく気がする。
「パリの恋人たち」のドアノーしか知らなくて、本橋成一って誰?の…わたしが見た物
二人の写真家は会う約束をしつつ、すれ違い、出会うことがなかった。
写真展の構成は、
ドアノーと本橋、2人が撮った同じテーマの写真を章ごとに展示してく。
・子ども・炭鉱と人々
・劇場と幕間
・街・劇場・広場
・遊園地
etc..エトセトラ
その街に・その場所に行き、人々の中に入ってシャッターを切ったであろう写真の数々。
展示された作品の、頭上には彼らのことば。
相手をこよなく愛してこそ、
写真を撮ることが許されるのだ -ロベール・ドアノー-
写真や映像は、相手に対する想いとイマジネーションだ -本橋 成一-
それらを吸い込みながら写真を見ていると、
本橋さんの写真からは
『撮らせてもらって良いかい?』と相手にたずねる声が聞こえてくるよう。
それくらい、人との距離感が丁寧で美しい。
けっしてむやみに隠し撮りしたようではありえない。
風景にさえ、そんな風に思えてくる。
写真を撮ることは、相手の一部におじゃまさせて頂く…ということ。
その一部にズカズカ踏み込んでいって、身勝手に切り取って良い訳ではない。
”そこに居て良い人”になり、”撮っていても良い人”になる。
あなたを傷つけたりしないよ、そういう人である…と思ってもらう。
一瞬を撮らせてもらうための準備が、カメラを構える前から始まっている。
彼らの写真を見ていると、溶け込む時間の大切さに気付く。
彼らがカメラを向けた先の人々は
「どうぞ撮ってくれ」という顔をこちらに向けている。
満面の笑み、静かな笑み、誇らしそうな顔。
カメラをパッと構えてパシャっとすぐ撮れる写真もある。
でもそれは、
相手がすでに受け入れてくれている(親子)関係があるとか
行った先の場所で事前準備が出来てる(地元の方の案内がある)とか
そこに至るまでのものがあるから…。
街並みですら、長い時間を積み上げてきたからこそ、そこにこうして在る。
幸せの喜びを分かち合いたいから
ただ見ることそれ自体が
幸せそのものに感じられる日もあっていい
その喜びが溢れんばかりになって、誰かと分かち合いたくなるんだ
-ロベール・ドアノー-
写真を撮る理由を問われたドアノーが返した答え。
なんて優しい視点なんだろう。
自分が注目されたいがためにSNSへ投稿する、"一瞬を切り取る行為"は同じでも、
それとは何かが一歩違う…。
慈しみのまなざしがそこにある気がする。
写真は、時間とともに
本の間に挟まった小さな押し花を思い起こさせるような
力を担ってくるのだ
-ロベール・ドアノー-
消費していくだけの写真ではなく、ときにずっと…何度も…見たくなる写真。
「どこに軸足を置いて君は写真を撮るのか」
「どこに軸足を置いて君は写真を撮るのか」あの言葉は、上野英信さんの生き方そのものだった。 -本橋成一-
写真を始めたばかりの本橋は、あこがれの先生を訪ねていって、こう言われたという。
本橋成一 インタビュー「本橋成一とロベール・ドアノー 交差する物語」展
インタビューでそのことについて語っている
その答えは、1991年、チェルノブイリ原発事故から5年後に訪れたウクライナ共和国を撮った写真に写っていたと思う。
『行ってね、何にもすることがないんですよね。それで支援のお手伝いをすることにして、おわったら村を歩いて…』
悲惨な事故があったのに、人々は日々の営みを続けていく。
そこには祝い事もあり、笑顔もあった。
そうして気づく
『”核”じゃなくて、すべて”いのち”だと思った。』
いのちをテーマに撮った写真は熱を放って輝いている気がした。
“Motohashi Seiichi & Robert Doisneau Chemins Croisés” PR movie
🎤展示フロア階のロビーで上映されていた、ドアノーの娘姉妹のインタビュー
見ているほどに気持ちが揺さぶられて、勝手に涙が止まらなかった。
帰宅後、この揺さぶられた感覚をどうにか書こうとしたけれど、うまく伝えられるような文がなかなか書けなくて、日が過ぎていった。
日が過ぎていくと記憶は薄れていくけれど、それを補うようにcamellのなかで起こる。、イベントや写真のテーマを考える機会がこの写真展を思い出させた。
《こどもの表情を生き生きと捉えるフォトグラファー松本周さんを招いた夜の写真トーク会!》
https://camell.town/events/ada5d6ed6e8d
『こどもと遊ぶ。こどもが楽しいのが一番。彼らが嫌がるときは撮らない』
《初めての作品撮りにトライ長期プロジェクト》
https://camell.town/events/cc44cdfff4db
テーマを決めて撮る。わたし何を撮りたいのか…。
ほかにも日々あげられるつぶやきや日記。...みんなの「撮る・写真」の想い。
毎日の生活の中で思い出すこと。出来事。
技は想いのためにある
”技は想いのためにある”…この言葉は、最初は「機材やテクニックを磨くよりも、気持ちを大切にしたほうが良い」的にとらえていて、やがて「想いを写し撮るためには、それを支える技や機材が必要」って捉えてた。
いまひとたびの変化。
写真のための写真を撮りたくない。
やがて、記憶のしおりになるような…そんなシャッターを切っていたい。
忘れられないシーンがあって、
残しておきたい想いにふれて、
それを誰かに伝えられたら…きっと素敵だろうと思う。
なにげなく押すシャッターの、その時。
構図や画角や光の方向、なぜ撮るのか、撮った写真をどう使うか。
頭で考えてカメラを構えるのではなく、
写しておきたい想いのままにシャッターを切った時。
知らぬ間に
構図や光を無意識にとらえていられたら、どんなにいいだろう。
いや、むしろそれもなくてもいい。
だって、レンズの向こうにあるものごとが素敵で
ただ美しくて
それが一番大切なことだから。
いまも・これからも、それを大切にしていたい。